|
浜松市天竜区の古城巡り
【鶴ヶ城跡】(320m)
4等三角点「羽生」(188.7m)
舩明山(3等三角点「舩明」)(283.9m)
行者山展望台(240m)
4等三角点「神谷沢」(228.6m)
3等三角点「山東」(435.2m)
【光明城跡】(489m)
光明山(2等三角点「光明山」)(540.3m)
【二俣城跡】(90m)
4等三角点「鳥羽山」(108.5m)【鳥羽山城跡】
平成29年5月3日(火・祝)晴
静岡県浜松市天竜区
今日は山菜採りに行こうとしていたが、それなら静岡県浜松市天竜区の古城巡りを兼ねてみようと思った。最近は浜松市天竜区の古城めぐりへ出かけている。3時00分に出発する予定であったが、寝坊して3時27分に自宅を出発した。こうした事態になっても単独なので、気が楽である。3時43分に関広見ICから東海環状自動車道に上がった。ゴールデンウイーク後半の初日であるが、さすがにこの時間帯は空いている。極めて順調で4時05分に土岐JCTを通過し、4時28分には豊田東JCTから新東名に乗り移った。しかし、さすがに新東名は車が多かった。4時54分に設楽長篠PAに入ったが、駐車場は大変混雑していた。空きエリアを探すのに苦労した。なんとかトイレ休憩を済ませ、5時26分に出発した。5時31分に新城ICから流出した。ここからは、国道151号を北上する。そして、JR飯田線の東栄駅を過ぎたら、県道1号線へ右折して、すぐに県道9号線へ右折する。この右折個所に「鶴ヶ城跡」の道標がある。飯田線の高架下をくぐって、南進する。すると、集落内に「鶴ヶ城跡」の道標があるので、左折する。するとすぐに荒れた林道となり普通車では通行困難となる。ちょうど荒れた林道になるところに駐車広場があったのでそこに駐車した。ちょうど6時00分であった。なお、左折して林道へ上がる手前に県道9号線の旧道があり、旧道に駐車した方がよいかも知れない。歩いても数1分か2分である。

(県道9号線からの入り口)

(左折地点の看板)

(駐車地点)
さて、準備をして、6時13分に出発した。まずは、林道をそのまま登っていく。6時18分に林道の終点らしい場所に着いた。

(林道終点)

(道標)
ここにも「鶴ヶ城跡」の道標があるので、この案内に従って左の山道へ入る。6時20分には登山道の分岐があり、ここにも「鶴ヶ城跡」の道標があった。

(分岐にも道標がある)

(竪堀の看板)

(道標)
また、竪堀という看板もある。ここで右の登山道へ入り、ジグザグに登っていく。6時23分に尾根に出ると、ここにも「鶴ヶ城跡」の道標と中部電力の鉄塔案内板「NO.13」があった。

(尾根上の道標)
案内に従って、尾根を右手へ進むと、すぐに「竪堀」と「土橋」の看板があり、さらに「馬出曲輪」の看板と小屋、「横堀」の看板もあって、6時26分に「本曲輪」の看板と小屋がある台地に出た。

(土橋の看板)

(竪堀の看板)

(馬出曲輪)

(横堀)

(本曲輪)

(土塁の看板)
ここが鶴ヶ城跡であろう。展望はない。6時32分に下山した。6時34分には尾根から降りた分岐を通過し、6時37分には林道に出た。林道を歩き、6時39分に駐車地点に戻った。
すぐに車をスタートさせ、「平賀屋敷」を探した。平賀屋敷は現在も民家らしく、隣に静岡県指定天然記念物の「佐久間のヒムロ」があるようだが、結局、見つからなかった。それで、あきらめて、次には光明城跡へと向かった。県道1号線を北上して、さらに国道473号へ合流して北上し、国道152号に出た。この国道152号を南下して、国道362号へと左折した。国道262号を少しだけ北上すると、「光明山遺跡」の看板がある。ここを左折すると、光明小学校の前に出る。ここで、右折して光明小学校を左に見て反時計周りに周回すると、「光明山遺跡」の看板があり、それに従って左折し、山麓へ向かうと、「林道光明線」の入り口がある。

(光明山遺跡の看板)

(林道光明線の入り口)

(光明山遺跡の看板)

(光明山遺跡の看板)
これが見つかれば後はこの林道を登っていくのみである。地形図を見ながら、4等三角点「羽生」の登り口を探しながら進む。すると、それらしき場所には2本の電波塔が建っていた。

(2本の電波塔の間の道へ入る)

(4等三角点「羽生」)

(4等三角点「羽生」)
2本の電波塔の間に車を駐車して、8時10分にそのまま先へと進む。すぐに道はなくなるが、そこから右手の高みを目指す。道はないが、藪はたいしたことはないし、距離にしてもわずかである。8時13分に高みのピークにある4等三角点「羽生」(188.7m)を発見した。植林に囲まれて展望はない。8時17分には下山した。8時18分に駐車地点に戻った。
すぐに車をスタートさせ、そのまま林道光明線を進む。林道には「光明山遺跡 あと○km」という看板があり、安心して進むことができる。次の目標は3等三角点「舩明」である。

(舩明山の登山口)

(登山口の看板)
登山口と思われる場所には「←行者山展望台 5分、舩明ダム方面 約30分」という看板があった。ここに駐車して、8時32分に尾根を忠実に登っていく。すると、8時41分に3等三角点「舩明」(283.9m)に飛び出した。

(3等三角点「舩明」)

(3等三角点「舩明」)
そばの木には「舩明山」という札が付いていた。この山は舩明山というのか。ここも植林に囲まれて展望はない。8時46分には下山した。8時49分に駐車地点に下り立った。ここで、行者山展望台の看板が気になって、行者山へも行くことにした。行者山へは尾根を登らず、トラバース気味に左山で下っていく明瞭な道があるのだ。8時50分に出発し下っていくと、8時54分には尾根乗り越しに出だ。

(登山道にある看板)

(道標)

(道標)

(看板)
ここには看板があり、「長養寺 舩明ダム方面 約30分」となっていた。また、「丸山製材団地方面 約30分」という看板もあった。ここで右折して尾根を登ると、8時57分に行者山展望台(240m)に着いた。

(遠景)

(行者山山頂の祠)

(展望)

(展望)
小さな祠があった。展望台という名はあっても木々が成長してあまり展望は望めなかった。8時57分には下山した。9時00分に分岐に出て、9時05分には駐車地点に戻って来た。
すぐに車をスタートさせ、今度は4等三角点「神谷沢」を目指した。神谷沢三角点への入り口と思われる場所には地形図にはない林道が分岐していた。

(光明山遺跡への道標)

(三角点「神谷沢」への入り口)

(中部電力の鉄塔案内板がある)
ここには中部電力の鉄塔案内板「NO.143」「NO.142」があった。この交差点に駐車して、9時16分に出発した。まずは新設林道を下っていく。この三角点へは藪漕ぎを覚悟していたが、林道があるとは実にありがたい。鉄塔を立てるために林道を新設したのであろうか。

(林道の終点)

(鉄塔)

(鉄塔そばの三角点)
9時21分に林道の終点に着いた。さらに先へと山道が延びていた。それを進むと、すぐの9時22分に鉄塔に出て、鉄塔のそばに4等三角点「神谷沢」(228.6m)があった。鉄塔の周りは樹林が伐採されているので、展望はよいが、いかんせん鉄塔から鉄塔方面が見えるだけであった。9時27分に下山した。下山といってもこの場合は林道の登坂となる。9寺34分に駐車地点に戻った。やはり往路より時間がかかった。
さて、すぐに車をスタートさせ、今度は3等三角点「山東」を目指した。林道沿いにこれだけ三角点があるのは珍しいと思う。おかげでいくつかの三角点を探勝することができありがたい。今度の「山東」三角点の登山口は地形図で破線の道が林道と交差している場所である。立派な道があり、大きな「山火事注意」の看板もある。

(三角点「山東」への登山口)

(登山口付近にある看板)

(鉄塔案内板もある)

(この登山道へ入る)

(公団造林の看板)

(3等三角点「山東」)
9時47分に出発した。9時50分に山道の分岐があり、山勘で右の道へと進む。左山で登っていくと、9時52分に山道がなくなり、そこには公団造林の黄色の看板があった。ここで、Uターン気味に左へ曲がって高みを目指す。9時54分に3等三角点「山東」(435.2m)に出た。これも植林に囲まれて展望はない。9時57分に下山した。9時59分に「公団造林」の看板の場所に出て、10時00分に分岐まで戻った。明瞭な山道をたどり、10時01分に駐車地点に戻った。
すぐに車スタートさせ、いよいよ光明城跡へと向かった。「光明山遺跡五十町」という看板がある駐車場に着いた。

(駐車場)

(駐車場)
10時12分に出発し、まずは看板に従って「方神塚」を目指し、坂道を登ると、10時16分に「方神塚」の看板がある平坦地(489m)に出た。

(方神塚への看板)

(方神塚の説明板)

(現在の位置と行程)
10時20分には下山した。10時21分に駐車場に戻った。今度は、本命の光明城跡へと向かった。こちらの入り口には中部電力の「大井川笹岡線 NO.132」という鉄塔案内板と「光明城跡」という道標がある。

(天龍光明の森)

(遺跡の森)

(光明城跡への道標)

(現在の位置と行程)

(光明寺跡へ着いた)

(遺跡の森)

(光明寺跡の看板)

(トイレ)

(保存会)

(展望)

(光明寺跡)

(光明寺跡)

(光明寺跡)

(展望図)
広い林道状の道を進むと、10時28分に光明山遺跡に出た。光明山遺跡はすごく広範囲にわたっているのだ。この場所は光明寺跡である。光明城跡でもあるが、光明城の場所に光明寺が寺院を建てたようで、城跡の石垣と思われるものは光明寺の石垣なのだ。光明城跡としては中曲輪、堀切しか残っていないという。

(光明城跡への道標)

(現在の位置と行程)
さて、ここからの展望を十分満喫した後、10時39分に光明城跡の道標に従って進んだ。10時42分に「←中曲輪」「堀切→」という案内板に出た。そばには「五人塚」の看板もある。

(光明城跡)

(光明城跡)

(現在の位置と行程)

(延命水)
ここが唯一残っている光明城跡だろう。10時46分にさらに先へと下ると、分岐があり、左へ曲がると、10時49分に林道光明線へ出た。それで、林道を戻り、10時59分に「延命水」を通過して、11時00分に駐車場へ戻って来た。
ここで、昼食休憩をとった。広い駐車場には誰もおらず、ゆっくりできた。お腹を満たし、この林道光明線の最後の目的地である光明山へ向かった。この光明山の登山口にも立派な看板があった。

(光明山登山口)

(天龍光明の森の看板)

(自然観察の森)
11時42分に出発した。木製の階段状の登山道を登っていくと、11時51分に「山頂広場」「奥之院」という道標のある乗り越しに出た。

(山頂への分岐)

(現在の位置と行程)

(光明山山頂)

(2等三角点「光明山」)

(光明山山頂)
左へ曲がって平坦状の道を進むと、11時53分に光明山山頂(540.3m)に出た。さすがにここからは展望が広がっていた。11時58分には下山した。12時00分に分岐に戻り、さらに奥の院へ行くことにした。途中に「霊峰富士山 景勝地」という看板がある場所に出たが、樹林のため富士山は見えなかった。

(霊峰富士景勝地)

(現在の位置と行程)

(分岐)

(奥之院)

(家康隠れ岩)

(天龍光明の森)
12時03分に「奥之院」「家康隠れ岩」という道標のある分岐に出た。12時05分に奥之院に着いたが、案内板も何もなく、清め水の石があるのみであった。ここから戻り、12時06分に「家康隠れ岩」に出た。さらに尾根道を進んで、12時08分に「天龍光明の森」という標柱のあるピークに出た。12時09分にここから引き返した。12時11分に「家康隠れ岩」を通過し、12時12分には分岐を過ぎ、12時14分に「山頂広場」への分岐も通過した。そして、12時19分に駐車地点に下り立った。
すぐに車をスタートさせたが、時間が正午を過ぎていたので、このまま帰ろうとしたが、それでも二俣城跡と鳥羽山城跡を見学することにした。

(駐車場)

(北遠の山城)
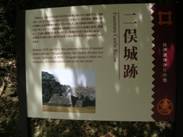
(二俣城跡)

(二俣城址)

(二俣城跡本丸)

(二俣城跡本丸)

(二俣城跡説明板)
国道362号で二俣まで戻り、二股城跡公園駐車場に着いた。13時05分に出発した。城山公園として整備されているので、登山装備はなくても大丈夫だ。13時08分に本丸跡地に出た。多くの市民がくつろいでいた。13時13分に下山した。13時b14分に駐車場に戻った。

(鳥羽山城跡登り口)

(鳥羽山城跡本丸)
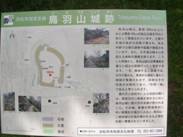
(鳥羽山城跡)

(本丸)

(4等三角点「鳥羽山」)

(展望)

(展望)
今度は、すぐ近くの鳥羽山城跡へ向かった。こちらも案内板があり、すぐに駐車場にたどり着いた。13時23分に大手道入り口からスタートした。13時24分に本丸跡に飛び出した。こちらも多くの市民がお弁当を広げていた。ここには三角点があるはずなので、休憩している市民を横目に三角点を探した。三角点は案内板もなく、苦労したが、4等三角点「鳥羽山」を発見して満足した。13時34分には下山した。13時35分に駐車場に下り立った。
これで今日の予定は終了し、帰路に就いた。とにかく連休後半の初日なので渋滞が心配なのだ。14時03分に浜松浜北ICから新東名に上がった。14時08分に浜松SAに立ち寄った。ここも混雑していた。14時14分に出発した。設楽長篠PAから岡崎東IC間で渋滞があった。おまけに渋滞の列で追突事故のすぐ後に遭遇し、渋滞に輪をかけていた。なんとか渋滞を抜け、15時06分に豊田東JCTを通過し、15時29分にときJCTを通過して、15時30分に五斗蒔PAに立ち寄った。15時18分に出発し、16時00分に関美濃JCTを通過して、16時02分に関広見ICから流出した。給油を済ませ、16時27分に帰宅したのであった。
(データ)
高速料金 4,410円
ガソリン代 3,830円
使用ガソリン 31.14㍑
平均燃費 13.0km/㍑