|
石老山(702.8m)
3等三角点「点名:石老山頂」(694.4m)
平成27年8月29日(土)雨
山梨県藤野町の藤野15名山
先立つものがないので、遠出を控えていたが、久しぶりに遠方の山へ行った。相模湖湖畔にある石老山(702.8m)である。最高点より少し下がったところに3等三角点「点名:石老山頂」(694.4m)がある。
8月中に取得可能な夏休みを取って、前日の28日(金)から出かけた。28日(金)は午前中に用事を済ませたが、午後からは雨が降り出してきた。雨の中、13時40分に自宅を出発し、14時07分に関ICから東海北陸自動車道に上がった。美濃関JCTで東海環状道に入り、14時36分に土岐JCTから中央道へ乗り入れた。雨が降ったりやんだりであった。14時55分に恵那峡SAでトイレ休憩し、15時20分にここを出発した。16時31分に岡谷JCTを通過し、17時10分に双葉SAに着いた。夜間と違って、昼間の移動は運転していても楽である。しかし、今日は金曜日なので、休日割引はない。それで、どこかのSAで車中泊して、日付をまたがないといけない。深夜の0時を過ぎれば深夜割引でも適用になる。車中泊するのはよいが、それなら暗くなる前に夕食を摂る必要がある。そんな訳で、車中泊の場所を談合坂SAと決めて、17時24分に双葉SAを出発した。17時54分に大月JCTを通過して、18時02分に談合坂SAに着いた。談合坂SAはなかなかよいSAである。SA内は人も車も相当混雑していた。小雨が降っていたので、テント内のベンチを見つけて、夕食の準備をした。食料、ビール、水、お茶、つまみは持ってきていたので、ガスストーブで料理をして夕食を済ませた。後は、することもないので早々に就寝した。レジアスエースの後部はフラットになり快適に眠ることができた。そんなに暑くもなく快適で、朝方は寒かった。
さて、29日(土)は、3時00分に起床した。小雨が降っていたが、身支度を整え、3時47分に出発した。3時59分に相模湖ICから流出し、登山口の駐車場がある、相模湖病院を目指した。カーナビにも「相模湖病院」と入力すれば案内してくれる。インターから国道20号へ出て左折し、「相模湖駅前」の信号で国道412号へ右折する。相模湖ピクニックランド入口を左手に見て通過してさらに進むと、「石老山入口」の信号がある。交差点には石老山入口と相模湖病院の看板がある。ここで、右折して、道なりに進むと、赤い橋を2つ渡る。2つ目の赤い橋を渡った先に左へ曲がるカーブがあるが、そこを曲がらず、直進(右折)する。

(左へ曲がらず、直進する。)
交差点には相模湖病院と石老山の看板がある。右への道へ入ると、道幅は狭くなり、道なりに坂道を上がっていく。すると、「石老山表参道入口」という看板と、続いて、「登山者・参拝者用駐車場」という看板が出てくる。駐車場の案内看板に従って右折すると、すぐに駐車場がある。

(駐車場)
駐車場は、病院通院者用のものと同じスペースにあり、登山者・参拝者用の駐車スペースは山側、車6台分くらいで狭い。しかし、早朝のため登山者・参拝者用の駐車場には1台もなかった。出やすいように一番手前のスペースに駐車した。小雨が降っていたので雨具を着けて、4時34分に出発した。登山道は駐車場と病院の間にある。登山者・参拝者用駐車場の奥から道が続いており、下って行くと病院のフェンスに突き当たる。ここで、左折し、フェンスに沿って進むと、すぐに沢があり、鉄製の橋が架かっていた。

(登山道の橋)
この橋を渡ると、いよいよ顕鏡寺までの参道となっている、石老山への登山道となる。

(滝不動)
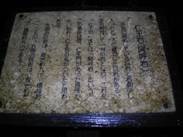
(仁王岩)
まず、4時42分に「滝不動」の前を通過し、すぐに「屏風岩」も過ぎて、4時45分に「仁王岩」に出た。

(駒立岩)
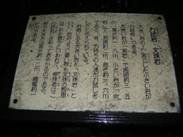
(力試岩・文殊岩)
4時49分に「駒立岩」を過ぎると、すぐに「力試岩・文殊岩」があった。そして、最後に石段を上がると、4時52分に顕鏡寺の前に出た。ここまでは、車で上がってくることができるようだ。しかし、駐車場がない。

(顕鏡寺前の道標)

(石段を登る)

(顕鏡寺の説明板)

(岩窟)

(岩窟の説明板)
さて、顕鏡寺山門の手前から左の石段を上がると、すぐに岩窟に出る。顕鏡寺の山号は石老山で、平安時代に源海法師によって創建されたということが書かれている。その源海法師が住居としたという「道志の岩窟」である。この岩窟の前を通り、左へ進むと鳥居があるので、この鳥居をくぐって石段を登っていく。
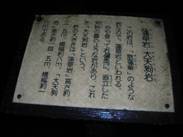
(蓮華岩・大天狗岩)

(分岐の道標)
4時57分には「蓮華岩・大天狗岩」を通過すると、5時01分に分岐に出た。左は八方岩を経由して山頂へ、右は桜山展望台を経由して山頂へという道標がある。どちらの道を登るか、しばし迷ったが、地形図からすると、八方岩経由のコースは、尾根を直登するようで、桜山展望台を経由するコースは、直登を避けて迂回するコースのようである。登りは八方岩経由で、下りに桜山展望台を経由することにした。

(鏡岩・小天狗岩)

(吉野岩・弁慶の力試岩)
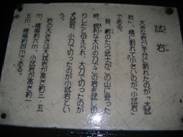
(試岩)
八方岩コースを登ると、5時04分に「鏡岩・小天狗岩」を通過し、5時08分には「吉野岩・弁慶の力試岩」を通過した。さらに5時11分に「擁護岩・雷電岩」を、5時12分に「試岩」をそれぞれ通過すると、5時16分に「八方岩」に飛び出した。

(八方岩展望台)

(八方岩)
展望は良さそうであるが、今日はガスっており、近くの山が見えるだけであった。ここからすぐのところで桜山展望台からの道が合流していた。ここからは、今までの急登とはうって変って緩斜面の登りとなった。

(融合平見晴台)

(融合平見晴台)

(融合平見晴台にある道標)
そして、5時25分に融合平見晴台に出た。ここからは相模湖の展望も良さそうであるが、ガスって見えなかった。ここには、「顕鏡寺0.8km、石老山バス停」、「篠原3.2km、石老山1.1km」の道標があった。緩やかな登山道を登っていく。5時43分には尾根上の小さなピークを越え、5時48分には左山で小さなピークを越えた。そして急な登りになったので、いよいよ石老山の山頂かと思われるピークに5時51分に出たが、このピークは山頂ではなかった。地形図によると、ここからいったん下って登り返したところが山頂のようだ。

(石老山山頂の道標)

(石老山)

(石老山)

(石老山の説明板)

(山頂標柱)
そして、5時55分に石老山山頂(702.8m)に飛び出した。ここには、「大明神展望台1.6km、篠原2.1km」、「顕鏡寺1.9km、石老山バス停」という道標がある。山頂からの展望はあまりよくないようだ。地形図によると、三角点は少し下がったところにあるようなので、6時01分にスタートして、篠原方面へ下ってみた。すると、6時03分に登山道の右手にある三角点を発見した。白い標柱もなにもなく、登山道から外れていたら発見できないところだった。

(3等三角点「点名:石老山頂」)
3等三角点で点名は、「石老山頂」(694.4m)である。ここからの展望もない。6時06分にUターンして、6時08分には石老山の山頂まで戻ってきた。高塚山(3等三角点「点名:山道」(675.5m))まで往復することも考えたが、この雨の中では行く気になれず、6時09分にこのまま下山することにした。6時12分に手前のピークを越し、6時」13分には右山でピークを通過し、6時16分には尾根上の小ピークを超えた。6時25分に融合平見晴台を通過して、6時30分には桜山展望台経由コースの分岐点に下り立った。ここから、桜山展望台方面へ左折して、6時37分に桜山展望台に下り立った。

なるほど、急坂を避けた迂回路であり緩やかな下りであった。展望台からは眼下に桜の幼木は見えたがガスのため遠望はできなかった。さて、6時41分に八方岩コースと合流し、6時43分に「蓮華岩・大天狗岩」を通過し、6時45分に顕鏡寺まで下ってきた。さらに、6時46分に「力試岩・文殊岩」と「駒立岩」を通過し、6時50分に「仁王岩」を、6時51分に「屏風岩」と「滝不動」をそれぞれ通過して、6時56分に駐車場まで下山してきた。雨の中の登山であったので低山ではあったが相当疲れた。また、雨も本降りの様相になってきた。そのため、相模湖から高尾山周辺まで観光ドライブとしゃれ込んだ。
さて、周遊観光を終え、18時11分に府中国立ICから中央高速道に上がり、18時19分に八王子料金所を通過して、中央道を西へ、19時17分に双葉SAに到着し、トイレ休憩をして、19時34分に出発した。20時49分から21時00分まで駒ヶ岳SAで休憩し、あとはノンストップで、19時37分に恵那峡SAを、21時40分に恵那ICを、22時09分に土岐JCTを、それぞれ通過して、22時41分に関ICから流出した。帰宅は22時59分であった。やはり夜の運転は疲れる。入浴して、すぐに寝てしまった。
データ
総走行距離 755.4km
使用ガソリン 83.84リットル
ガソリン代 10,339円
平均燃費 9.0km/㍑
高速代 11,980円
車 レジアスエース2000cc