|
鶏松(高根山)(点名:日長)(48.4m)知多市
天神山(25.5m)知多市
老眼山(点名:野間村)(111.0m)美浜町
秋葉山(84m)南知多町
雨山(97.7m)(点名:大井村)南知多町
任坊山(51.4m)(点名:任坊山)半田市
平成25年12月22日(日)晴
愛知県知多市、美浜町、南知多町、半田市
今日は、天気予報では、積雪情報もあるため、南方面で知多半島の超低山を登りに出かけた。事情があって高速は使えないため、一般道でトロトロと行く。出発は、5時45分であった。国道22号の木曽川大橋では、日の出を待つ人がいた。冬至の今日は、伊勢神宮内宮では、鳥居の真ん中から日の出が拝めるという。この木曽川大橋からは、138タワーからの日の出が見えるのか?それは定かではないが、とにかく車を進め、名古屋市内を抜けて、東海市へ、さらに知多市へと入る。そして、名鉄古見駅を目指した。この付近は車道の幅が狭いので、大型の車では通行に慎重にならざるを得ない。最初の目標である鶏松(高根山)は、名鉄の古見駅の南約800mにある。あとは、地図読みの技術であろう。新知保育園の裏山にある「神道大教 古見御嶽神社」が鶏松(高根山)であるらしい。

新知保育園の入口に車を止め、8時36分に御嶽神社へと石段を登って行く。

この石段は正面ではなく、正面から見ると、右側の石段である。すぐの8時37分には、御嶽神社に出た。左に正面からの石段が上がってきている。

右手には本殿がある。

本殿の右側には「神道大教 古見御嶽神社」という表札がかかった社務所がある。

また、本殿の左側の奥には、集会所のような建物がある。ちょっとした広場と簡易トイレもある。しかし、あるはずの三角点は見つからない。「点名:日長」という3等三角点があるはずなのだが。神社の境内なのだからすぐ見つかると思ったが、発見できなくて残念である。


8時42分には下山した。8時43分に駐車地点に着く。山登りというより三角点探しであるが、その三角点が見つからないのはすっきりしない。
しかし、次の目標である天神山へ向かうことにした。天神山は同じ名鉄の2つ先の駅、日長駅の近くである。しかし、この日長駅を見つけるのに、苦労した。とにかくこの付近は道路幅員が狭すぎる。普通車では通行できない個所もあり、Uターンも出来ず、バックで戻る場面もあった。何やかやで苦労してやっと、日長神社にたどり着いた。「紅葉谷」という案内板があった。日長神社の鳥居の前まで車で上がることができる。しかし、普通車では道路幅の狭さに苦労する。いつもは、軽自動車で来るのに今日に限って普通車で来ていたのでヒヤヒヤであった。そんな訳で日長神社まで車で上がったので、9時33分に神社から石段を下った。すると、9時34分に石段下の鳥居に出る。そこから右手へ歩いて行くと、9時37分に日長駅に着いた。









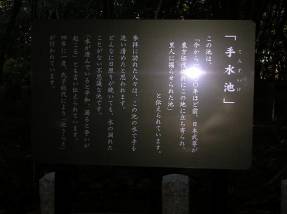
そこからUターンして、9時39分に鳥居に着き、石段を登ると、9時41分に本殿に着いたというわけである。本殿の近くに駐車場もある。また、駐車場のそばに「手水池」があります。この天神山には三角点はない。
次は、美浜ICの近くの「鍋山(81.6m)」へ登ろうとしたが、どうしても登山口へたどり着けず、諦めて次の山へ向かった。美浜オレンジラインが通り、登山口からすぐだというのであるが、その美浜オレンジラインが、地形図では車道のような広い道になっている。当然、車で通行出来るものと思ったが、普通車では無理である。通行止めの標識はないが、車道幅が狭くて物理的に無理なのだ。車の側面や底部を擦ることを覚悟でいくならよいが。
さて、今度は、美浜町の老眼山を目指した。国道155号は国道247号に変わり、南下していく。美浜町の「小野浦」地区から「美浜少年自然の家」の看板で左折する。すると、すぐに「美浜少年自然の家」の駐車場に着く。

10時47分に駐車場を出発した。


とりあえず、少年自然の家へ向かい、10時52分に建物の正面に出た。

さて、ハイキングコースはどこかなと、自然の家の敷地案内図を見た。反時計回りで周回することにして、「ロマンの広場」へ向かった。



11時00分に「ロマンの広場」に着いた。

ここにはハイキングコースの道標と、美浜生活環境保全林の大きな看板があった。この看板の前を通り、林道のようなハイキングコースを登って行く。すぐに右手にキャンプ場の炊事場がある。


ここを通過すると、左の尾根へ登る階段があり、展望台への道標がある。

ここから階段を登ると、11時02分に尾根に出た。ここにも道標があり、「右は展望台、左はのぞみの丘、手前はロマンの広場」となっている。当然に右の展望台を目指す。さらに階段を登ると、ピークに出て平坦な尾根歩きとなる。11時06分に右手から階段が上がってきて合流している。左からは林道のような広い道が上がってきている。正面には展望台が見えたので、そこへ行ってみた。展望台というからには、三角点があるかも知れないと思った。11時07分に展望台に着いたが、三角点らしき物は見あたらない。11時10分にここで引き返して、11時11分に合流点まで戻った。正面(右)の谷を隔てた先に2つのピークが見える。その左側のピークが目指す老眼山であろう。そして、林道のような広い道を下って行くと、11時13分にこの林道から左へ分岐するハイキングコースがあった。



展望台への道標を無視してハイキングコースをそのまま登ってくると、ここへ出るものと思われた。さて、ハイキングコースの道標に従ってここから階段を登っていくと、11時16分にピークに出た。ここにもハイキングコースの道標があった。ここからは、緩やかな尾根道を進むと、11時17分に「老眼山」と思われるピークに出た。

三角点があるはずだがと探すと、ハイキングコースの右手奥の笹藪の中に白い標柱と三角点が見つかった。




2等三角点「点名:野間村」である。せっかくハイキングコースで整備してあるなら、せめて三角点の周囲だけは笹を刈り払いしてもらいたいものだ。でも三角点が見つかって満足した。11時23分には下山した。復路は往路をたどらず、せっかくのハイキングコースなのでそのまま周回することにした。階段を下ってくると、11時29分に林道のような広いハイキングコースに出た。

ここにはハイキングコースの道標があり、いま下って来たのは、「ハイキングコース アドベンチャー」で、合流したのは、「ハイキングコース ウッディー」ということらしい。ハイキングコースのウッディーを下っていくと、11時31分に池畔に出た。右手に池をみながらハイキングコースを歩いて、11時32分に「ふれあい広場」という野外炊事場がある場所に出た。さらに進むと、11時34分に少年自然の家に着いた。そして、ここから石段を下って、11時36分に駐車場へ戻った。
早速、車中で昼食を摂り、次なる目標の「秋葉山」へ向かった。名鉄の内海駅を通り、まっすぐに進むと、左手にある内海中学校の横を過ぎて、持宝院に突き当たる。持宝院にも駐車場はあるが、秋葉山へはまだ距離があるので、車で進むことにした。しかし、この作業道は道幅が狭くて普通車では苦労した。いつもの軽自動車で来ればよかったと後悔したがいまさらどうにもならない。持宝院の入口手前で左折して、作業道を登っていく。すぐに秋葉神社への山道があり、車1台分の駐車スペースもあった。ここに駐車して歩けばよかったが、僅かな歩きを惜しんだためさんざんな目にあった。この作業道は山腹に植えられたミカン畑への作業道である。道幅は車幅一杯一杯で待避所もない。防風のために両側に植えられた夾竹桃の枝やミカンの枝が張りだして車の側面を擦る。ゆっくりと慎重に車を進めると、ピークに出て、そこには山神八神を祀る石碑があった。


ここが山頂なのかと思ったが、ここにも秋葉神社の道標があったので、秋葉神社はもっと先らしい。しかし、普通車でこれ以上進むのは諦めた。ちょうど、このピークがロータリーになっていたので、ここに車を駐車した。
12時01分に秋葉神社を目指して歩き出した。ミカン畑の中を歩き、ミカン畑の終わりから坂道を登ると三叉路があった。地形図のとおりである。


この三叉路で右へ曲がると、すぐの12時07分に秋葉神社に着いた。三角点はない。12時11分には下山して、12時16分に駐車地点へ戻った。また、神経をすり減らして狭い道を下った。
さて、次は「高峰山」を目指したが、登山口が見つからないので諦めて、雨山(97.7m)「点名:大井村」を目指すことにした。豊浜魚港(高浜)からの県道281号線入口を見落としたので、師崎まで行ってしまい、県道7号線(半田南知多公園線)で戻った。「観光農園花ひろば」を通過して、すぐ崎(東)の農道を右手(南)へ入る。すぐに感慨用のため池があるので、その脇の広場に駐車した。目の前のこんもりとした丘が雨山(点名:大井村)であるはずだ。13時07分に出発し、どこかに取り付き点があるはずだと探しながら南へと農道を進む。13時08分に案の定山の尾根の鞍部へ上がる踏み跡が見つかった。雨山は小さいながらも独立峰のようになっているのだ。雨山から南へ延びる尾根の鞍部に取り付くようになっている。ここから鞍部に上がったが、ここから尾根を雨山へたどる道は完全に薮に埋もれている。薮をかき分けて無理矢理登っていくと、竹藪となった。ところが手入れがしてないので、見通しも利かず歩きにくいことこのうえもない。とにかく高い所を目指して進み、13時16分に雨山山頂の2等三角点「点名:大井村」を発見した。2等三角点なのだからもう少し手入れをしてほしいものだ。


三角点の上にうまい具合に獣の糞が乗っていた。また、付近にプラスティックの杭があったので、まるっきり人が来ないわけでもないようだ。ただ、登山の対象にはなっていないということであろう。さて、13時20分には下山したが、こんな手軽な超低山で迷ってしまった。何も登山道具を持っていなかったが、山を甘くみてはいけないと改めて痛感させられた次第である。南への尾根を忠実に下ればよかったのであるが、左より(東より)に下ってしまったのである。すぐに気がついたからよかったもののパニックになるところであった。なんとか、最初に上がった尾根の鞍部にたどり着き、13時26分に農道へ下り立った。そして、13時27分に駐車地点へ戻ってきた。よかった。
さて、もう知多半島の先端まできているので、あとは戻るしかないが、帰りに半田市の任坊山「点名:任坊山」(51.4m)へ登ることにした。
半田ICの近くにある半田市の市立図書館、博物館の駐車場に車を止めた。ここから南へ歩いた方向に三角点があるはずだ。14時35分に出発して整備された階段を登っていく。「人和風土」という大きな石碑があった。さらに登っていくと、山頂は平らな平坦地になっている。



樹林があり見通しは悪いが遊歩道を歩いていくと、14時36分歩道の脇に三角点があった。よく整備されている。14時39分に下山した、14時40分に駐車場へ戻った。南への展望がよい展望台があるらしいが、見つけることができず、下山してしまった。山頂の北の図書館から登ったためであろう。任坊山公園があり、駐車場もあるらしい。
知多半島の低山巡りは、これで終了したが、こころ残りなのは高峰山と鍋山へ登れなかったことである。帰路も一般道をとおり、18時00分に帰宅した。
翌日、改めて高峰山と鍋山へ登りに行ったが、またしても鍋山の登山口が分からず、無念の撤退であった。とにかくゆっくりと歩いて巡るのであればよいが、駆け足で巡ろうとするなら、軽自動車で来ないといけない。鍋山の近くを通る、美浜オレンジラインは、軽自動車ならいいが、普通車では通行に苦労する。