|
点名:城跡(838.7m)
点名:弥高山(495.2m)
平成25年10月27日(日)晴れ
滋賀県米原市
さて、今日は、関ヶ原町今須の三角点「点名:妙応寺」を探し当てて満足して、さらに近くの滋賀県米原市の三角点「点名:城跡」と「点名:弥高山」を探しに行った。
関ヶ原町から、国道365号を西進し、滋賀県へ入ってすぐの信号交差点で右折して広域農道へ入る。「弥高川」を渡ってすぐの信号交差点で右折する。

右折すると、伊吹山の南麓を伊吹山へ向かって上がっていく感じである。


右手にある川は弥高川である。突き当たってから左へ曲がり、すぐに鋭角で右へ曲がる。いずれも曲がる場所に「悉地院」の看板がある。

そしてすぐにその「悉地院」が左手にあり、それを過ぎて登っていくと、今度は左手に採石場がある。

採石場の右端を登っていく。右手には「弥高川」がある。採石場を過ぎると、弥高川を渡って、さらに急坂を上がると、右へのヘアピンカーブがある。採石場からここまでも相当悪路であるが、このさき更に悪路になるので、車はこのヘアピンカーブに駐車した方がよさそうだ。私は、さらに登って行ったが、すぐにチェーンのゲートにより行く手を阻まれる。地形図によるとこの林道は、「点名:弥高山」まで通じているのだ。「点名:矢高山」はこの林道のすぐ脇にあるというべきか。なお、地形図には麓の「弥高地区」から登山道があるように破線で描いてある。

さて、林道はペアピンカーブのすぐ先に分岐があり、目指す方向はチェーンで閉鎖されている。従って、ここに駐車して歩くしかない。10時42分に出発した。チェーンを乗り越えて林道を登っていく。チェーンがなくても荒れており、車の通行は無理であろう。
林道を上がってくると、見晴らしのよいところがある。そして、10時55分に「地蔵堂」への分岐点に出た。

丁度、下からも地形図では破線の登山道が上がってきており、この付近に「点名:弥高山」があるはずだと探して見たが見つからなかった。

左へ曲がると、すぐの10時56分に地蔵堂があった。林道をそのまま上がるより、地蔵堂経由の道の方が近いので、地蔵堂の前を通って、荒れた林道(地形図の破線の道)を登って行った。すると、11時01分に林道へ出た。林道を左へ曲がってさらに登っていく。

11時10分に左へ分岐する林道があったが、そのまま直進する。左手の高みに鉄塔があったので、分岐する林道は、その鉄塔へ行く林道かもしれない。さて、林道を直進すると、11時14分に終点広場に出た。思ったより整備されている。トイレもあるし、登山届BOXもあり、案内看板もある。またまた、他県の登山道整備状況に感謝し、感心するほかはない。


終点からの登山道は2つあり、どちらへ行くべきか迷った。看板は、一方の登山口には「弥高尾根道 ←至 伊吹山5合目」「弥高寺跡経由で桐ヶ城(上平寺)跡」という看板があり、もう一方の登山口には、「桐ヶ城(上平寺)跡近道」「宝篋印塔を経て上平寺城跡へ 伊吹山歴史と自然の登山道」という看板がある。手持ちの地形図には看板の示す場所のいずれも記載がない。また、伊吹山5合目という看板には驚いたが、広域の地形図を持って来なかったので、伊吹山5合目へのルートが想像出来なかった。唯一想像出来るのは、地形図には「京極氏遺跡」と描いてある場所であろうということだ。上平寺城は京極氏の居城であり、京極氏は織田信長の妹お市の方の娘(茶々、お初、お江の3姉妹)のうち2女の「お初」が嫁いだ先である。私の頭では、京極氏は、関ヶ原の戦いの後から頭角を現してきたと理解している。弥高寺と上平寺城についての勉強不足が一番いけなかった。

11時20分、迷った結果、「近道」という文字に惹かれて、「桐ヶ城(上平寺)跡近道」という登山道へ入ってしまった。

11時25分に「一本杉」への看板があり、右手へ下る道が分岐していた。

これを過ぎると、11時27分に「

11時32分に分岐があった。ここには、「

このすぐ先に「薬師谷の遺構 伊吹山歴史と自然の登山道」の看板があり、右へ分岐する道があった。また、「←桐ヶ城(上平寺城)跡 弥高寺跡→」という看板もあり、ここを11時26分に出発した。相変わらず左山のトラバース道が続く。そして、11時45分にこのトラバース道が終わり、下りになった。「これはまずいぞ。」と思いながらも少し下ると、11時26分に明瞭な登山道に出た。これが、「京極氏遺跡」から登ってくる破線の登山道であろうと判断した。合流点には「伊吹山5合目へ 伊吹山歴史と自然の登山道」という看板と、「↑伊吹山5合目 ←弥高百坊 上平寺」という札が付けてあった。このまま下っていけば上平寺城跡、つまり京極氏遺跡へたどり着くのであろう。しかし、今日は上平寺城跡は諦めて、「点名:城跡」を目指すため、伊吹山5合目の方へと左折して、登っていくことにした。かつては、立派な登山道であったろうと、思われる道が続いている。

12時08分に分岐に出た。この分岐には、「上平寺城跡へ 伊吹山歴史と自然の登山道」という看板と、「伊吹山5合目へ 伊吹山歴史と自然の登山道」という看板がある。また、「↑弥高 ←上平寺 →伊吹山」という札も付けてある。この分岐を過ぎると、12時14分にピークに出た。正面に伊吹山がそびえている。

このピークに「点名:城跡」があるはずだ。ススキが生い茂っている。ススキをかき分けると、木に白い札が付いていた。山名板と思われるが、文字が消えており判読できない。

また、5m程離れた他の木には、赤いテープが巻いてあった。よく山頂で見かけられるテープである。だから、この付近に三角点があるに間違いないと確信した。それで、30分かけて探し回ったがどうしても見つからなかった。それで、諦めておにぎりを食べて、伊吹山を眺めながら休憩した。天気はいいしとても気持ちがよい。昼寝でもした気分だったが、帰宅して温泉へ入ってビールでも飲もうと、12時44分には下山した。12時45分に分岐に来たので、下山は、往路ではなくて、弥高寺跡を経由する道を下ろうと、分岐で右へ曲がった。12時50分に「大堀切 弥高寺本坊跡」という看板と、「伊吹山5合目へ」という看板のある場所に下り立った。


そして、12時54分に弥高寺跡に出た。ここには、「桐ヶ城(上平寺城)跡」の看板があり、この看板に従って行くと、往路で通った分岐へ行くものと思われる。さて、この弥高寺跡は、たいそう広い広い平坦地となっている。

かつては、大きな寺院があったのも納得できる。米原市街地や琵琶湖の展望が素晴らしい。林道終点からここまで登って来るだけでも十分満足出来る。ワンゲル例会に使うとすれば、ここまでであろう。12時58分にここから下山した。

13時00分に「大門跡」を通過して、13時04分に林道終点へ下り立った。「
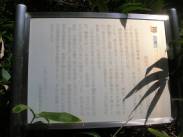
さて、あとは林道を歩き、13時07分に林道分岐から近道を通り、13時15分に地蔵堂の所へ下ってきた。すると、地蔵堂の前に人がいた。驚いたのなんのって、心臓が止まりそうになった。相手は、私の熊鈴のおかげで人が来るのは分かっていただろうが、私は突然であったのだから。その人は、ここまで登ってきたが、この先行けるのかと私に聞いてきたが、道はありますから行けますよと答えた。また、熊が出るだろうかとも聞かれたので、大丈夫でしょうと答えました。そして、私は、この付近にあるであろうと思われる「点名:弥高山」の三角点を探した。付近は笹の薮で極めて見つけにくかったが、なんとか13時19分に探し出すことができた。




付近の木に「弥高山 495.2m」というイセ愛山会の山名札が付けてあった。三角点は地蔵堂と林道との間の斜面にあった。かつては、こちらが登山道であったのだろう。いまは、地蔵堂への道を緩やかなものに付け替えたものと思われる。
さて、その人は、私が三角点を探して射るうちに林道を下ってしまったようだが、私は、三角点の発見に満足して、13時26分に林道を下った。13時34分にゲート前の駐車地点に戻った。
今日は、ここまでとして、帰路についた。上平寺跡への登り口を確認して、15時05分に帰宅した。いつものように三田洞神仏温泉へ入浴に行き、そのごビールを飲んでくつろいだ。