|
�y�@�K�@�x�i�Q�C�O�T�Q���j
�\�@���@�x�i�Q�C�O�V�V���j
�g�����E�V�R�i�Q�C�P�S�P���j
��@�ʁ@�x�i�W�U�U���j
�M�@�O�@�R�i�P�C�O�S�P���j
�����Q�T�N�V���P�R���i�y�j�`�Q�P���i���j
�k�C��
����̖k�C���̍s���܂����B�S���R��ڎw���l�ɂ͓��R�Ȃ��猇�������Ƃ��ł��܂���B���̉����䂦�ɂȂ��Ȃ������ł��܂���ł����B�����̋x�ɂ����˂Ȃ�܂���B�������A�ƂƂ��ɐ����䂭�̗͂͂�����Ƃ����������A���s���̂��A���s���̂��Ǝ��⎩�������A�u���ł���I�I�v�ƈ�̂������������ƂɁA���s���邱�ƂɂȂ�܂����B
���āA�k�C���ւ̉��H�͑����m�t�F���[�ŁA���É��`���V���P�R���i�y�j�̂P�X���O�O�����ł����B�P�S���R�O���Ɏ�����A�֎s�łj���ƍ������A���É��`�ւƌ������܂����B�o�`�̂Q���ԑO�����D�葱�����J�n�����ƕ����Ă����̂ŁA�P�V������ڕW�ɂ��Ă������A�����x��̂P�V���P�T���ɖ��É��`�t�F���[�^�[�~�i���ɒ������B��D������A�����r�[���ŏo�w�����s���B���Q�̃r�[���Ƃ��܂݂ʼn�����n�߂��B����Ȓ��A�t�F���[�͒荏�ǂ���ɏo�`�����B�����m�t�F���[�́A�Ϗ��q�`�֒��s�ւł͂Ȃ��̂ŁA���`�Ɋ�`����B���̂��ߓϏ��q�`�܂ŁA�P����������̂ł���B���C�ɓ�������f���������b��������肵�ĉ߂����B�P�S���i���j�̂P�U���S�O���ɐ��`�ɒ������B�����āA��q�̉��D�A��D���s���A�ݕ��̏o��������s���A�R���Ԍ�̂P�X���S�O���ɓϏ��q�`�Ɍ����ďo�`�����B�܂��܂��A�剃������đD�����y���B
�����āA�P�T���i���j�̂P�P���O�O���ɗ\��ʂ�Ϗ��q�`�ɓ��`�����B���悢��k�C���ɓ��ݓ��ꂽ���ƂɂȂ�B���̎R�s���́A���ꂼ��̎v�f������A�O���͕ʁX�̍s���ŁA�㔼�ɍ������ē���s������邱�ƂɂȂ��Ă����B����ŁA�܂��u�C�I���v�ŐH�����B���s���A���łɒ��H��ۂ��Ă���j�����i�q�Ϗ��q�w�܂ő������̂ł������B���̌�A�j���͂i�q�ňړ����ăA�|�C�x�֓o�邱�ƂɂȂ��Ă����B�����́A�y�K�x�̓o�R��n�ƂȂ��Ă���L�f�R���ւƌ��������B���������ԓ��ŕx��h�b�܂ōs���A��������͍����Q�R�V���i���������j��k�サ���B���������ɂ́u�y�K�x�v�o�R���̑傫�ȊŔ�����̂ŁA�ԈႦ�邱�Ƃ��Ȃ��B

�����Q�R�V������E�܂���ƁA���Ƃ͈�{���Ōj�����z����ƖL�f�W���ɓ���B

�L�f�R���́A�W���̓����߂��ɂ���A�Z�ɂȂ����L�f�����w�Z���������āA�o�R�җp�̏h���{�݂ɂ����炵���B


�P���Q�H�łT�C�O�O�O�~�Ƒ�P�Q�[�g�܂ł̃V���g���o�X�̉����^���R�C�T�O�O�~���x�����āA�h�����ɓ������B�h�����͂Q�i�x�b�g���U��łP�Q�l����ł������B�撅���ōD���ȏꏊ������̂ŁA��ԓ����ɋ߂��x�b�h�̉��i���m�ۂ����B�����͂P�U������H���͂P�V������Ƃ����̂ŁA����܂ł̓r�[�������݂Ȃ��瓯�h�̓o�R�҂ƎG�k�����ĉ߂������B�P�U����������ł���̂ŁA�����ɓ��������B�Q�`�R�l���炢�����P�x�ɂ͓���Ȃ��B�ꏏ�ɓ��������l�́A���䌧�̕��ŕS���R�͂W�U�R�o���Ă���Ƃ����B���������ł��ƎR�k�`�ɉԂ��炢���̂ł������B

�[�H�̓W���M�X�J����łǂ����Ă����Ȑl�ɂ͓��ʂɑ��̗���������Ă����Ƃ����B�����ł��r�[����Ў�ɃW���M�X�J����������B�����̏o���͂R���O�O���ł���̂ŁA�[�������邱�ƂȂ����X�ɂQ�i�x�b�g�ɂ����肱�B�������A�������I�I�ׂ̐l�̂Ђǂ����т��őS������Ȃ������B
���P�U���i�j�́A���悢��y�K�x�ւ̓o�R�ł���B�Q���܂����炲�������Ə������n�߂�o�R�҂������̂ŁA���������������ė①�ɂ��璩�H�p�̂��ɂ�����ĊO�ɏo���B���ɂ���͂S�p�ӂ���Ă���B���H�ƒ��H���l���Ă̂��Ƃł��낤�B���̂��ɂ���͌�ŐH�ׂ邱�Ƃɂ��āA�o������O�ɂ͎��Q�����p����H�ׂ��̂ł������B�O�֏o��ƁA���͏o�Ă��Ȃ������̂ŁA�V�C�͂��܂�悭�Ȃ��̂��ȂƎv�����B�V���g���o�X�́A�Q���R�O������ɂ͖L�f�R���̑O�ɓ��������B�^�]�肪�_�Ă����A�o�X�ɏ�荞�B�荏�̂R���O�O���Ƀo�X�͏o�������B�{���̎n���̏�q�͂P�S�l�ł������B���ƂŁA�킩�������Ƃ����A���̂����P�R�l�͖y�K�R���ɗ\�Ă������A�P�l�͓��A��Ȃ̂ł������B�V���g���o�X�͗\��ʂ�R���T�V���ɑ�P�Q�[�g�ɓ��������B

��P�Q�[�g�ɂ͉������ƃg�C��������B���A��ł��ŏI�̃V���g���o�X�ɊԂɍ���Ȃ�������A���̉��݂̋x�e���ň����߂������ƂɂȂ�B���āA�o�R�҂́A�V���g���o�X�������Ƃ����ɗѓ�������n�߂��B�������x��܂��ƂS���O�O���ɕ����n�߂��B�܂��A�搅�{�݂܂Ŗ�Q���Ԃ̗ѓ������Ȃ̂��B��ɏo�������o�R�҂�ǂ��z���Ȃ���A����}�����B�S���Q�O���Ɂu�搅���ւU�D�O�����A��P�Q�[�g�ւP�D�T�����v�Ƃ����\��������ꏊ��ʉ߂����B

�S���Q�V���Ɂu���y�K���v��n��A�S���T�Q���ɕ�����A�u�y�K�x�v�̈ē��ɂ���ĉE�ւƐi�ށB�S���T�U���Ɂu�搅���ւR�D�O�����A��P�Q�[�g�ւS�D�T�����v�Ƃ����\����ʉ߂����B���̐�Ő擪������Ă����o�R�҂ɒǂ������B�b�����킷�ƁA���A��̗\��Ȃ̂ł����܂ŋ}���ŗ������ǂ��ɂ��P���ԂR�O���Ŏ搅���ɒ��������ł���B����Ȃ���A�肪�\�ł���Ɗm�M�����ƌ����Ă����B�n���̃V���g���o�X�̏�q�P�S�l�̂����P�l�������A����v�悵�Ă����̂ł���B�����ŃU�b�N�͏��������A�}���ŕ����Ă����킯���B����Ȃ�ƁA���������̐l�ɂ��čs����̂ł���A���A����\�ł��낤�ƁA�Ђ����ɓ��A����˒����ɓ��ꂽ�̂ł������B

�����āA�T���R�P���Ɏ搅���֓��������B���傤�ǂP���ԂR�O���ł������B

�����ŁA���A��҂���̂T���R�R���ɏo�������B�܂��́A�z����̉E�݉����̓o�R����o���Ă����B�N�T���ɂ��܂��āA���`���Ă����ꏊ�����邪�A�Ƃɂ����s����Ƃ���܂ʼnE�ݑ��������̂ڂ��Ă����B���̉E�݉����̓��œ��A��҂ɒǂ��z���ꂽ�B�����āA�E�ݑ��ɓ����Ȃ��Ȃ�ƁA��������n���n�܂�̂��B


�U���O�T���ɑ�P�n�n�_�ɏo���B���A��҂��n�̏��������Ă����B�����������n�̏��������āA�U���P�T���ɓn���J�n�����B

�E�݂��獶�݂֓n��ƁA�U���P�U���ɑ�Q�n�n�_�i���݁��E�݁j�ł���B

����ɂ����ɑ�R�n�n�_�i�E�݁����݁j�ɂȂ�B

����ƁA�Ί݁i�E�ݑ��j�ɑꂪ�����Ă���B

���炭���ݑ���k�s���A�U���Q�O���ɑ�S�n�n�_�i���݁��E�݁j�ɏo��B



����ɂU���Q�S���ɑ�T�n�n�_�i�E�݁����݁j�A�U���Q�V���ɑ�U�n�n�_�i���݁��E�݁j�A�U���Q�X���ɑ�V�n�n�_�i�E�݁����݁j��ʉ߂��āA���̂��Ƃ��炭�͍��ݑ���k�s���čs���B

�����āA�U���S�R���ɑ�W�n�n�_�i���݁��E�݁j���߂���ƁA�E�ݑ��̓o�R����o���čs���B




�U���S�T���ɑ�X�n�n�_�i�E�݁����݁j��n��A���ݑ���k�s���āA�U���S�V���ɑ�P�O�n�n�_�i���݁��E�݁j���߂��E�ݑ���k�s���āA�U���T�O���ɑ�P�P�n�n�_�i�E�݁����݁j���߂����ݑ���k�s���āA�U���T�S���ɑ�P�Q�n�n�_�i���݁��E�݁j���߂��ĉE�ݑ���o���čs���B

�U���T�V���ɑ�P�R�n�n�_�i�E�݁����݁j��ʉ߂��č��݂�o���čs���B

�V���O�S���ɑ�P�S�n�n�_�i���݁��E�݁j���߂���ƁA���炭�E�ݑ��̓o�R����o���čs���B

�����āA�V���P�P���ɑ�P�T�n�n�_�i�E�݁����݁j�ɏo��ƁA�Ί݂ɂ͎��т̒��̖y�K�R����������B���ꂪ�Ō�̓n�ƂȂ�B���߂ĂP�T��̓n�ł������B�V���P�X���ɖy�K�R���ɒ������̂��B�����܂łɐ��P���b�g��������Ă����B
���A��҂͐�ɓ������Ă����B����ɐg�y�ɂȂ��Ėy�K�x�ւƌ������Ă������B�������x��܂��ƁA�o�R�C�ɗ����ւ��A�����ȃU�b�N�ɉJ��Ƃ��ɂ�����l�ւ��āA�V���R�S���ɖy�K�R�����o�������B�����Ȃ�̋}��ł���B�ѓ���n�̔�ꂪ�o�Ă����̂��s�b�`���オ��Ȃ��B�W���R�X������W���T�O���܂ŋx�e���āA���ɂ����H�ׂ������ǂ��Ă��܂����B���̑̒��s�ǂ͂ǂ����ĂȂ̂��H�����ς茴�����킩��Ȃ������B����ł������܂ŗ�������ɂ͎R���܂˂Ȃ�Ȃ��B�y�K�R���͗\�Ă���̂�����A�}�����Ƃ�����܂��B���₢����A��҂�ǂ��A���������A�肷�邱�Ƃ��ł��邼�B�Ɗ������Ȃ���o���Ă����B�����āA�悤�₭�X���P�X���Ɂu���̐�v�ɒ������B�����܂łɐ�������ɂO�D�T���b�g��������Ă����̂ŁA�����łO�D�T���b�g����⋋�����B

�X���R�P���Ɂu���̐�v���o�����A�}��̊��ؑт���ƂX���T�W���ɗŐ��ɏo��B

�p�b�ƓW�]���J���āA�ڎw���y�K�x���p�������B�ڕW�������Ă���ƁA�ӗ~���N���Ă���B���̕t�߂ł͖y�K�R���ɏh�����Ă����o�R�҂����R���Ă���B

���艺�ɃJ�[�������Ȃ���A�����v���ɗŐ������ǂ��Ă����B�R�����ʂ̓K�X�����������萰�ꂽ�肵�Ă����B



�P�O���Q�O���Ƀs�[�N���z���A�P�O���S�Q���ɂ��s�[�N���z���āA����ɍ��x���グ�Ă����B����ɂP�O���T�S���ɂ��s�[�N���z�������A���̕t�߂œ��A��҂����R���Ă����B�A��̃V���g���o�X�̎������C�ɂȂ��ċ}���ʼn��R���Ă����Ƃ̂��Ƃ��B


����������Ɏm�C���グ�ēo��A�P�P���O�T���Ɂu�V���R�[�X�v�Ƃ̍����_�ɏo���B���������R���ł���B

�����āA�P�P���P�Q���ɖy�K�x�R���i�Q�C�O�T�Q���j�ɏo���B�R���ɂ͒N�����Ȃ������B�������A�W�]�͑f���炵�������B�D�V�Ɍb�܂�Ă悩�����B�����ŁA�P�R���܂łɖy�K�R���܂ʼn��R�ł���V���g���o�X�̍ŏI�ւɏ���ł��낤�ƌv�Z�����B

����Ȃ킯�ŁA�P�P���P�X���ɉ��R���J�n�����B�P�P���Q�T���Ɂu�V���R�[�X�v�̕���_�ɗ����̂ŁA�V���R�[�X�̓o�R����`���Ă݂�Ƃ������}�o�ł������B�}���Ŗ߂�A�U���R�[�X�i���H�j�������Ă������B���̕t�߂���n���̃V���g���o�X�ł���Ă����o�R�҂Ƃ���Ⴄ�悤�ɂȂ����B�P�P���R�V���A�P�P���R�X���A�P�P���T�O���Ƃ��ꂼ��s�[�N���z���āA����ɍ��x�������A�P�Q���O�U���ɂ͂��悢��Ő�����}�������悤�ɂȂ����B�P�Q���Q�O���Ɂu���̐�v��ʉ߂��A���H�ŋx�e�����n�_���P�Q���R�R���ɒʉ߂����B�����āA�P�R���O�S���ɖy�K�R���ɉ��藧�����B���̎��_�œ��A������f���A�y�K�R���̗\����L�����Z�������B
�R���̊Ǘ��l�ɂ́A�V���g���o�X��Ђɂ͍ŏI�ւɏ�邱�Ƃ�A�����Ă�������Q�ĂȂ��悤�Ɉ��S���ʼn���悤�ɂƂ����āA�P�R���P�S���ɎR������ɂ����B�P�R���P�T���ɑ�P�T�n�n�_�i���݁��E�݁j��n���Ă��炭�E�ݑ��̓o�R��������A�P�R���Q�S���ɑ�P�S�n�n�_�i�E�݁����݁j��n���č��ݑ�������A�P�R���Q�W���ɑ�P�R�n�n�_�i���݁��E�݁j��n��A�P�R���R�P���ɑ�P�Q�n�n�_�i�E�݁����݁j��n��A�P�R���R�T���ɑ�P�P�n�n�_�i���݁��E�݁j��n��A�P�R���R�V���ɑ�P�O�n�n�_�i�E�݁����݁j��n��A�P�R���R�X���ɑ�X�n�n�_�i���݁��E�݁j��n��A�P�R���S�P���ɑ�W�n�n�_�i�E�݁����݁j��n��A���炭���ݑ��������Ă����B�����āA�P�R���T�T���ɑ�V�n�n�_�i���݁��E�݁j��n��A�����P�R���T�U���ɑ�U�n�n�_�i�E�݁����݁j��n��B����ɓn�͑����A�P�R���T�W���ɑ�T�n�n�_�i���݁��E�݁j��n��A�P�S���O�O���ɑ�S�n�n�_�i�E�݁����݁j��n���āA���ݑ��ւ���ƁA�Ί݁i�E�ݑ��j�ɑꂪ������B�����āA�P�S���O�S���ɑ�R�n�n�_�i���݁��E�݁j��n��A�P�S���O�U���ɑ�Q�n�n�_�i�E�݁����݁j��n��ƁA�P�S���O�W���ɍŌ�̑�P�n�n�_�i���݁��E�݁j�ɏo��B������P�S���O�X���ɓn��I���n���I�������B�����A�o�R�C�ɗ����ւ��āA�P�S���P�X���ɏo�����A�E�ݑ��̓o�R���������čs�����B�P�S���T�P���Ɏ搅�{�݂ɓ��������B��������͂P���ԂR�O���̗ѓ������ł���B�������A��ꂽ�̂ɂ͐h�������B�P�T���R�O���Ɂu�搅���ւR�D�O�����A��P�Q�[�g�ւS�D�T�����v�̒n�_��ʉ߂��A�P�T���R�T���ɂ͉E����̗ѓ��������āA�P�U���O�R���Ɂu���y�K���v��ʉ߂����B�P�U���P�R���Ɂu�搅���ւU�D�O�����A��P�Q�[�g�ւP�D�T�����v�̒n�_���߂��A�P�U���R�S���ɑ�P�Q�[�g�̃V���g���o�X�̔�����ɒ������̂ł������B��P���ԂS�O���̗ѓ������ł������B
�V���g���o�X�͒荏�̂P�V���O�O���ɏo�����A�P�W���O�O���ɖL�f�R���ɒ������B�P���̗\�肪���A��ƂȂ����̂ŁA���ꂩ��ǂ����悤�ƍl�������A�Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�Ȃ��̂łƂ肠�������̗\��ł���\���x�̓o�R���ւƌ��������B
�\�@���@�x�i�Q�C�O�V�V���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�T�N�V���P�V���i���j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C����x�ǖ쒬
���āA�k�C���̕S���R�Q�߂́A�\���x�ł���B�y�K�x����A�肵�ĖL�f���獑���Q�R�V���֏o�āA�����Q�R�V����k�サ�ď�x�ǖ쒬���瓹���Q�X�P�����i�����x�ǖ���j�։E�܂��āA�u�]�x��v���ԏ�ւQ�O���T�O���ɂ��ǂ蒅�����B����̎Ԃ����Ԃ��Ă����B���X�g�n�E�X�O�̒��ԏ�͂Q�i�ɂȂ��Ă���A���i�ɂ̓��X�g�n�E�X�ƃg�C��������A��i�͒��ԏ�Ɠo�R���ł������B���R�A�r�[��������ł��Ă����̂ő����r�[��������ŏA�Q�����B


�����ĂP�V���i���j�̂T���R�O���ɓo�R�����o�������B�ŏ��͍L���o�R���Ŋɂ₩�ɓo���Ă����B�U���Q�O���ɔ��l�x�Ə\���x�Ƃ̕���_�ɒ������B�u�\���x�A���l�x�A�]�x��v�Ƃ������W�ƂƂ��Ɂu�\���x�R�D�Q�����A�]�x��Q�D�O�����A�W���P�C�Q�U�O���v�Ƃ����\�����������B

�����ʼnE�܂�āA�\���x��ڎw���B�㕔�Ɂu�\���x�����v�������Ă����B

�U���R�Q���ɂ��́u�\���x�����v�ɒ������B�����ŋx�e���A�U���R�W���ɏo�������B
���փg���o�[�X���đ��n��A�K����̔�����o���Ă����B�U���S�U���Ɂu�\���x�����]�x��v�Ƃ������W�Ɓu�\���x�Q�D�V�����A�����O�D�Q�����A�]�x��Q�D�T�����A�W���P�C�R�W�O���v�Ƃ����\�����������B�U���T�T���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�V���O�Q���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�V���P�Q���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�V���P�X���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�����ʉ߂��āA�V���S�U���ɏ��a���Ό��ɏo���B

�����ɂ́u�]�x�䁩���\���x�v�Ƃ������W�ƂƂ��ɁA�u�\���x�P�D�U�����A�]�x��R�D�U�����A�W���P�C�V�Q�O���v�Ƃ����\�����������B


�\���x���ڂ̑O�ɔ����Ă����B�o�R���������邪�}�ȃK�����o��˂Ȃ�Ȃ��B�V���S�W���ɂ������o�������B�V���T�S���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���߂��āA�V���T�W���Ɂu�]�x�䁨�v�̓��W���߂���B�W���O�U���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W��ʉ߂��A�W���O�X���Ɂu�\���x�O�D�V�����v�̊Ŕ��߂����B����Ɋ���₷���K����̋}���o��A�W���R�P���Ɂu�]�x�䁨�v�Ƃ����Ŕ̂���ꏊ�ɏo���B

�\���x�̌��Ƃ����������̂Ƃ���ł���B�u�O�\���R�[�X�@�ʍs�֎~�v�̊Ŕ�����B

�����x�e���A�W���R�R���ɏo�������B�R����ڎw���čŌ�̋}��ł���B�q�[�q�[�n�[�n�[�����Ȃ���A�W���S�V���ɂ���Ə\���x�R���i�Q�C�O�V�V���j�ɏo���B


���炵���V�C�ő�W�]���L�����Ă����B�R���r�j�Ŕ����Ă����T���h�C�b�`��H�ׂċx�e�����B���͂P���b�g��������B����g�����E�V�R�֓o�����Ƃ����v�w�A�ꂪ�����̂ŁA�����g�����E�V�R�̃z�b�g�ȏ����d���ꂽ�B
�����āA�X���O�R���ɉ��R���J�n�����B�X���P�P���Ɂu�]�x�䁨�v�̊Ŕ��A�X���Q�R���Ɂu�\���x�O�D�V�����v�̊Ŕ��A�X���Q�T���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�X���R�O���Ɂu�]�x�䁨�v�̊Ŕ��A�X���R�Q���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W�����ꂼ��ʉ߂��A�X���R�U���ɏ��a���Ό��܂ʼn����Ă����B�x�e�͂���������}���A�X���S�X���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�X���T�Q���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�X���T�U���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W���A�X���T�X���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W�����ꂼ��ʉ߂��A�P�O���O�Q���Ɂu�]�x�䁩���\���x�v�̓��W�Ɓu�\���x�Q�D�V�����A�����O�D�Q�����A�]�x��Q�D�T�����A�W���P�C�R�W�O���v�Ƃ����\��������ꏊ��ʉ߂����B�����āA�����ɑ��n��g���o�[�X���āA�P�O���O�V���Ɂu�\���x�����v�ɒ������B��������L���o�R���ƂȂ�A�P�O���P�S���ɔ��l�x�ւ̓o�R���ƍ������āA�P�O���S�S���ɓo�R���ւƉ����Ă����B����ł͐����O�D�T���b�g��������B�������ɐl�C�̎R�Ƃ����āA�ό��o�X�����Ă������A�o�R�҂ƎU��҂Ƃ����荬�����Ă����B�܂��A���ԏ�͖��t��Ԃł������B
�\�肪�P�����܂����̂ŁA�����P�S���R��o�낤�ƍl�������A�k�C���͍L�����Ĉړ���������������B�����̗[���ɂ͂i�q�V���w�ő҂����킹�ł������B�ƂĂ������P�̎R�֓o�鎞�Ԃ͂Ȃ��̂ŁA�g�����E�V�R�ɔ����āA�����͂������Ƌx�{���邱�Ƃɂ����B
�܂��́A�]�x��̋߂��́u����I�V�̓��v�֓��邱�Ƃɂ����B�Ȃ�Ƃ����Ă������Ƃ����̂������B���͈Â��ē���Ȃ������̂ł������B����A���ꂽ�����m��Ȃ����A����Ȃ������̂ł���B
����I�V�̓�
�����Q�T�N�V���P�V���i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C����x�ǖ쒬
�@�\���x���牺�R���āA���������ɖK�ꂽ�B�Ԃ͐��䂵�����Ԃ��Ă��Ȃ������B���͉���͒��ԏꂩ��P�T�O���قǕ����˂Ȃ�Ȃ��B���������̏��������Ă���ƁA����A���Ă����l���A�i���o�[�����āu����ł����H�v�Ƙb�������Ă����B�u�����ւ�悢���ł��B���o�Ă��܂������A���傤�ǒj�����R�l�������Ă���A�Ă��܂���B���邩���ɂ��܂��ĕ����悤�ɁB�v�Ƃ������Ă����B



�@����֑������������Ă����ƁA�����Ɏ��т̊Ԃ��牷�����Ă����B�Ǘ��l�͂��炸�A�ȈՒE�ߏ�������B


�܂��A�n���肷���K�i����������Ă���B���炩�������łƂĂ��悢�B�J���ŗ�܂��Ă���悤���B���痬��o�Ă��闬��ɐG��Ă݂�Ƃ����ł������B�͂����Ȃ������Ȃ̂ŁA�o�X�^�I���␅���𒅗p���Ă��悢�Ɛ�������������B
���D�̑��̉����Ȃ̂��A���������ق������B�������A���x�Ƃ�������͉��K�ł������B���̂����A�����̒j�������ē���������A�����������Ȃǂǂ������������ꂽ�B�l���������Ă����̂œK���Ȃ��날���ɑގU�����B
�@���āA���̌�͂ǂ����ό��ł����悤���ƁA�Ƃ肠�����A��x�ǖ�̎s�X�n�܂ʼn����Ă����B
���̏o����
�����Q�T�N�V���P�V���i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C����x�ǖ쒬
����I�V�̓����牺���Ă��āA��x�ǖ�̃X�[�p�[�Ńr�[���Ƃ܂݂����ꂽ�B�����āA���̏o�����Ƃ����ꏊ�ɗ����B�������ԏꂪ���邵�A�g�C�����������Ă���̂ŎԒ����ɂ��傤�Ǘǂ��B�����ŎԒ����ƌ��߂đ����r�[���ŏj�t���グ���B�T�}�[�x�b�h�����o���āA�؉A�ɃZ�b�g���ăr�[�������������ƈ��B



���ʂɂ͏\���x�����ꂢ�Ɍ����A���x���_�[���˂̒n�炵���A���x���_�[�𒆐S�ɑ��̉Ԃ����ꂢ�ɐA�����Ă���B�u�˒n�̂悤�Ȍ����ɖ��Ă���̂��B�����̎U��͌�ɂ��ĂƂɂ����r�[�������B�o�R�����ĉ���ɓ������ゾ���ɂ��܂������B
���āA�j���̗l�q�����߂Ƀ��[��������ƁA���������\��ʂ�œϏ��q�ւ̐ؕ����Ƃ��낾�Ƃ����̂ŁA������͂P���\�肪�����Ȃ����̂Ŗ����͋Ă��邩��A�Ϗ��q�w�܂Ō}���ɍs�������Ƃ����ƁA����͂��肪�����Ƃ����̂ŁA�����͂X���O�O���ɓϏ��q�w�O�́u���[�g�C���Ϗ��q�w�O�v�z�e���܂Ŗ߂邱�Ƃɂ����B


�r�[���̌�͈ꖰ�肵�����A�������ɖk�C�x�A���������Ə������B�[���ɂȂ��Ă�����A�����̐l�����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�������̎U��ɏo�������B�u�̏�ւƑ����U���H��o���Ă����ƁA�W�]��ƃg�C�����������B�u�̏�̓W�]��܂ŎԂŏオ���Ă�����悤���B�܂��A�������ɂ̓I�[�g�L�����v�T�C�g������B�Ȃ��Ȃ����͋C�̂悢�����ł���B��x�ǖ씪�i�ƂȂ��Ă���炵���B



�[���ɂȂ�ƁA�y�̃L�����s���O�J�[�̕v�w���b�������Ă����B�u�����Ŕ��܂�܂����H��X���h������̂ł�낵���B�v�Ƃ������Ƃł������B������͈�ʎԂł��邪�A�������̓L�����s���O�J�[�Ȃ̂ŋ߂��̐l�������ɗ��Ă����B���͊W�Ȃ��Ƃ���ɗ[�H�p�Ɏ��Q�������������A�ʋl���܂݂Ƀr�[�������ݎn�߂��B�[�ł�����O�ɕЕt���ĈÂ��Ȃ�Ɠ����ɏA�Q�����B�������A��ʎԂ̒��ł͈����ł��Ȃ��B
���āA�����P�W���i�j�́A�P������ɋN���o���āA���̏o�������o�������B���H�����̂܂ܖ߂����ŃJ�[�i�r���Z�b�g�������A�J�[�i�r�͈�����ʂ��ē����Ă����B����Ŗ������č����Q�R�V����쉺�����B�Ƃ��낪�A�r���ł������Q�R�V���ł͂Ȃ��A�����R�W��������ʂ֍s���悤�Ɏw�������Ă���B�n�}�Ŋm�F���Ă����炩�ɉ����Ȃ̂����������g���悤�ɃZ�b�g���Ă���̂����m��Ȃ��B���Ԃ͂����Ղ肠��̂�����A�J�[�i�r�̈ē��͂�߂āA�����Q�R�V�����Ђ�����쉺�����B
�r���ŁA�`�o�����ɗ�����������A�x�����ŕ�����Ă����B���ɋ`�o�_�ЂƂ����̂�����̂�m������������̍Ղ�ł������B



�����āA���̉w�u�ނ���l�G�̊فv�ɗ������ƁA�����C������Ă����̂ő������������B
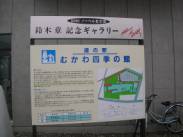




�����āA�Ϗ��q���`�A�Ϗ��q���`�̃t�F���[�^�[�~�i�����������āA�R���r�j�ŕX���d����A���H��ۂ��ă��[�g�C���z�e�����������B�W���S�O���Ƀz�e���̒��ԏ�ɒ������B
�g�����E�V�R�i�Q�C�P�S�P���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�T�N�V���P�X���i���j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C���V����
�P�W���i�j�W���T�O���Ɂu���[�g�C���Ϗ��q�w�O�v�z�e���ŁA�j���ƍ������āA�g�����E�V����ւƌ��������̂ł������B�����܂ł͂��ܗ������������Ԃ����ƂɂȂ�B�����������ԓ����獑���Q�R�V�����o�R���ē������֓���A���̉w�u���C���[�h�����v�ɗ���������B


���������X����H�X�͋x�Ƃł������̂ŁA���߂č����Q�V�S���œ��������z���Đ������֓������B�V�C�͂悩�����̂ł��邪�A�������͔Z���ł������B�s�v�c�Ȃ��̂Ő������ɉ����Ă���Ɛ���n���Ă���̂ł���B�������Œ��H��ۂ����B�ው�̏ē�����H�ׂ��B����ɐV�����̃R���r�j�Ŗ����̐H�����d����āA�����V�P�W�����Ńg�����E�V�����ڎw�����B��������P���ԂR�O���قǓ������R�̒��Ƀg�����E�V����͂���̂��B
�g�����E�V����������ʼn��̏W���͕x���n��̂悤�ŁA�����ɂ͕x���������w�Z������B�����艜�ɂ͖��Ƃ͂Ȃ��A�g�����E�V����́u�����h�ɓ���ᑑ�v�́A��ԉ��Ƀ|�c���Ƃ���ꌬ�h�ł���B


�P�S�����ɓ��������̂ŁA�`�F�b�N�C������O�ɖ����̒Z�k�o�R�����m�F���邽�߁A����ɗѓ������ւƎԂŐi�����Ă������B�Z�k�o�R���Ƃ����ē������邵�A��{�I�ɂP�{���Ŗ������ƂȂ��A����ᑑ�����Q�O���œo�R���ɓ�������B�������A������͂��邵�A�ł��ڂ�������̂ŁA���ӂ��Ēʍs����K�v������B


�Z�k�o�R���̒��ԏ�͎v�������L�������B�R�ӏ��ɕ�����Ă��邪�A���ꂼ��אڂ��Ă���A���v�ł͂P�O�O�䂭�炢�͒��Ԃł������ł���B�o�C�I�g�C��������B�܂��A�������̎Ԃ��c���Ă����B�܂��A���R���Ă��Ȃ��̂��A���邢�́A���A��łȂ��e���g���̎Ԃł����낤�B
���āA�������I���ē���ᑑ�֖߂�A�`�F�b�N�C�������B�����͂Q�S���ԉ\�ł���B�[�H�͂P�V���R�O������Ƃ����̂ŁA����܂ŁA���Q�����r�[��������A�R�C�������h���[�Ő����肵�ĉ߂������B�����ɂ͗①�ɂ�����A�����̃r�[�����₷���Ƃ��ł���B�܂��A�����q�ɘA�������߂Ă��邭�炢������A���R��������Ȃ��B�����A�N�[���[�{�b�N�X�̕X�X�I�ɂ���ē��点�Ă������B
���P�X���i���j�́A�S���O�O���ɓo�R�����o������\��ł������̂ŁA�R���O�O���ɋN�����A���₭���������ĂR���R�O���ɓ���ᑑ���o�������B�o�R���̒��ԏ�ɒ���������ɂ́A���邭�Ȃ��Ă����B�����̓o�R�҂����������Ă����B��X���o�R���̓o�R�͂ɋL�����āA�S���O�S���ɋC�������ďo�������B���߂͕��R�Ȏ��т̒��̓o�R���ł���B����ɓo��ɂȂ�A�S���Q�Q���ɂ̓g�����E�V����o���Ă���{���Ƃ̍����_�ɏo���B


�{���𗈂�Ƃ����܂łɂQ���Ԃ�����킯���A�Z�k�o�R������͂Q�O���Ȃ̂ő����Z�k����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B�����ɂ́A�u�g�����E�V�R�W�D�T�����A�o�R���R�D�R�����A�Z�k�o�R���O�D�V�����v�Ƃ������W������B�V�C�͉����ŋC�����オ��B�X�������Ȃ��Ă���ƁA�������o���B�S���R�R������S���R�U���܂ő̉����߂̂��ߋx�e�����B�S���S�O���ɃR�u���z���B

�����āA�S���T�O������S���T�Q���ɂ��x�e���āA�T���O�V���ɃJ���C�V��ɓ��������B

���̐悷���A�T���O�X���ɂ͐V���Ƌ����̕���ɏo���B�������A�����͂������Ɖ����Ă���ƂĂ����ݍ��߂��Ԃł͂Ȃ��B�u�V�����v�Ƃ����Ŕ�����݂̂ł���B

���̐�Ő�k���������肷��B�T���P�V������T���P�X���܂ŋx�e�����B���̕t�߂͊�{�I�ɔ����������Ă��������Ȃ̂ŁA�\���x�∮�x�̓W�]���������������ċC�����a�炮�B�܂��A�g�����E�V�R���ʂ̓W�]���J���Ă���B�����āA�R�}�h����։��~�����O�̑�̂Ƃ���ŁA��l���x�e���ł������̂ŁA��X���x�e�����B�U���O�T������U���P�R���܂ŋx�e���āA���H�p�̂��ɂ����H�ׂ��B
���āA��������́A�R�}�h��������āA�W�����P�O�O�����}�~�����邱�ƂɂȂ�B�U���Q�X���ɑ�ɉ��藧�����B���̑�́A�J���C�T���P�i�C��ł���B��͎c�Ⴊ�������B�J���C�T���P�i�C��̉E�ݑ��̐�k��������̂ڂ�ƁA�U���R�X���Ɂu�R�}�h����v�ɏo���B


�u�R�}�h����v�Ƃ����W���͎c��̂��߁u�R�}�h���v�܂ł��������Ȃ��B���̕��͐�ɖ��܂��Ă���̂��B���ꂭ�炢�̐ϐ�ʂ��Ƃ������Ƃ��B�R�}�h����͉E�ݑ��֗������Ă���̂ŁA�����ŁA�E�݂ւƓn���āi��k�̏�Ȃ̂œn�͂Ȃ����Ȃ��B�j�R�}�h����̐�k�����n�߂��B

��k�͒��o�Ȃ̂ő������B�������A���x�͉҂���B�w��̎R�X���O���O���Ƃ��肠�����Ă���B�V���O�R���ɂ͐�k���I���A��̑����o�R���ɂȂ�B


����ɁA�V���O�X���ɂ͉E�����փg���o�[�X������̓o�R���ɂȂ�B�����܂łɐ��P���b�g����������B�g���o�[�X���I���ƃK����̃W�O�U�O�̓o��ɂȂ邪�A���т���̂ŁA�W�]���J���Ă���B�����āA�}�ȎΖʂ�o�肫��ƕ��R�n�ɂȂ邪�A���ꂪ�u�O�g�����v�ƌ�����ꏊ�ł���B

�V���R�R���Ɂu�O�g�����v�ɓ��������B�V�C���悢�̂ŁA�W�]�����炵�����C������X�ł���B�V���R�T���ɑO�g�������o�������B��������Ζʂ�o��ƁA�P�����̂���������z���ɏo��B

�V���S�T���ɃP������ʉ߂����B�����܂ŗ���ƃg�����E�V�R�������Ă���B����Ɋ���o���āA�V���T�Q���ɃR�u�ɏo��B

���̃R�u���牺�����ƕ��̕��n���u�g�����E�V�����v�ł���B

���́u�g�����E�V�����v�ɂ͂W���O�P���ɓ��������B�����ŁA�G�l���M�[��⋋�����x�~���āA�W���O�X���ɏo�������B

��k����̃g���o�[�X�����Ȃ��A�W���T�O���ɓ�����ʂƃg�����E�V�R�R�����ʂ̕���_�ɒ������B

������u�g�����E�V����v�Ƃ����邱�ƂƂ��낾�B�u�E��̓g�����E�V�R���A����̓I�t�^�P�V�P�R�A�\���x�A��O�̓g�����E�V����v�Ƃ������W������B�����ł����x�~���āA�W���T�U���ɏo�������B

��������̋}�o�������������A�X���Q�R���ɑҖ]�̃g�����E�V�R�R���i�Q�C�P�S�P���j�ɗ������B�u������[�v�Ƃ�������ł��܂��B


�����܂łɂ���ɐ��O�D�T���b�g����������B�����ł��f���炵���W�]�Ɋ������グ��B���ǁA�o��ɂ͂T���ԂQ�O�������������ƂɂȂ�B
�R���ɂ͏c���̓o�R�҂�s�X�g���̓o�R�҂ȂǁA�����̓o�R�҂��������A���ꂼ�ꉺ�R���čs�����̂ŁA��X���C���ł�����������Ă���ꂸ�A�X���S�U���ɂ͉��R�ɂƂ肩�������B�u�g�����E�V����v���P�O���O�U���ɒʉ߂��A�u�g�����E�V�����v�łP�O���S�S������P�O���S�U���܂ŋx�e�����B��������o��Ԃ��āA�P�P���O�O���ɃR�u�����z���A�P�P���O�U���ɃP�������߂���B�ቺ�Ɂu�O�g�����v���L�����Ă���B���̑O�g�����ɂ́A�P�P���P�Q���ɉ��藧�����B�G�l���M�[�⋋�̂��߁A�P�P���P�V���܂ŋx�e�����B��������}�Ȋ��̎Ζʂ�����A�����g���o�[�X���Đ�k�֏o���O�ŁA�P�P���Q�X������P�P���R�S���܂ŋx�e�����B���̌�A��k�������āA�u�R�}�h����v�ɂ͂P�P���S�S���ɉ��藧�����B�P�P���S�W���܂ŋx�e���A��̉E�݂������āA�o��Ԃ��̏ꏊ�ɏo���B�����ŁA�P�P���T�S������P�P���T�U���܂ŋx�e���āA���悢��o��ɂ�����B���̓o���o������Ƃ���ŁA�P�Q���O�W������P�Q���P�P���܂ŋx�e�����B���H�ŋx�e���Ē��H��H�ׂ���̂Ƃ���͂P�Q���P�V���ɒʉ߂����B�P�Q���S�Q������P�Q���S�T���܂ŋx�e���A�V������ł́A�P�Q���T�W������P�R���O�O���܂ŋx�e�����B���̌�A�u�J���C�V��v���P�R���O�P���ɒʉ߂��A�P�R���P�V���ɃR�u�����z���A�{���ƒZ�k�o�R���Ƃ̕���ɂ́A�P�R���Q�U���ɉ��藧�����B�����ŁA�P�R���R�R���܂ŋx�e�����B�����āA�Z�k�o�R���ւ͂P�R���S�V���ɉ��藧�����̂ł������B����ł́A���O�D�T���b�g����������B����͂S���Ԃ��������B�����ł͋x�e���܂߂āA�X���ԂS�O���ł���B�g�����E�V�R�͉����R�Ƃ������Ƃ��B
�����ɎԂ��X�^�[�g�����A�ѓ��𓌑�ᑑ�܂Ŗ߂����̂ł������B���̓��͓���ᑑ�ł������Ɖ���ɐZ��������A�j�t���グ���̂͂����܂ł��Ȃ��B�����Ė������ɕ�܂�ďn�������̂ł������B
��@�ʁ@�x�i�W�U�U���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�T�N�V���Q�O���i�y�j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C����Ύs
����̖k�C���̎R�s���Ōv�悵�Ă����S���R�́A�\��ʂ�o��I���ĂQ�O���i�y�j�́A����₩�ȋC���̗ǂ������}�����B�����Ƀg�����E�V����̕����U���B
�����́A�����A�邾���Ȃ̂ł��邪�A�t�F���[�̏o�`�����͂Q�R���O�O���ł���A�������Ԃ�����̂ŁA�ǂ����̎R�֓o�낤�Ƃ������ƂɂȂ�A��ʊx�Ɍ��肵���B
����ᑑ����߂�ѓ��Ńq�O�}��ڌ������B���̌�A���_��W�]��œW�]�i���āA���E�ւƉ����Ă����B�����āA���������ԓ��ɏ���Ďx┌������A��h�b�ō~�肽�B�������瓹���P�U�����Ŏx┌Εt�߂ō����S�T�R���֓���B�x┌Γ��݂̎x┌Ή�����߂���Ƃ����ɖ�ʊx�o�R���̊Ŕ�����B���̊ŔʼnE�܂��ĎR�[�̕��֏オ���Ă����ƁA�m�s�s�h�R���̐�p���H�ƂȂ�A�����ɂ̓Q�[�g������B���̎�O�ɒ��ԍL�ꂪ����A�V�`�W�䂭�炢�͒��Ԃł��邪�قږ��t��Ԃł������B����ł��ǂ��ɂ��X�y�[�X�ɒ��Ԃ����B���傤�lj��R���Ă����o�R�҂������̂ŁA�Г��P���ԂR�O���ł��邱�ƁA���̂m�s�s�h�R���̐�p���H������Ă����ΎR���ɒB���邱�ƂȂǁA������肵���B



�P�Q���P3���ɏo�������B�P�Q���P�V���ɃQ�[�g�ɒ������B�Q�[�g�̉��ɓo�R�̓{�b�N�X���������B���́A���̓o�R�̓{�b�N�X�̘e����o�R�����������̂����A�C�Â��Ȃ������B�o�R�҂͂��̖w�ǂ��ԓ�������ēo���Ă���悤�Ȃ̂ł���B�����A���̌�������炩�̉��R���Ă���l�����Ƃ��������̂ł���B����Ȃ킯�Ŏԓ�������ēo���Ă������B

�r���ɋ����\��������A�P�Q���S�X���ɂ́u�Q�W�S�X���^�Q�O�O�O���v�Ƃ����\���̏ꏊ��ʉ߂����B�܂�A���̂m�s�s�h�R���̐�p���H�́A���������S�W�S�X���ŁA��������Q�O�O�O���o���Ă��āA�R���܂ł͂Q�W�S�X�����Ƃ������ƂȂ̂ł���B�ԓ�������Ă���ƁA�R���ɂ���A���e�i�Q���T�ˌ����Ă���B�オ���Ă���ɂ�Ďx┌�M�O�R�A���s���x�̓W�]���J���Ă������A�����̂͏����B�k�C���֗��Ă��܂܂ł͗������ɋ��������A�����͏����B�ܑ����H�Ȃ̂ŁA�Ƃ�Ԃ������邽�߂Ȃ̂�������Ȃ��B����ł��K�}�����ēo���Ă����B�P�Q���T�Q���Ɂu�Q�U�S�X���^�Q�Q�O�O���v�̕\�����A�P�Q���T�U���Ɂu�Q�S�U�X���^�Q�S�O�O���v�̕\�����A�P�R���O�O���Ɂu�Q�Q�S�X���^�Q�U�O�O���v�̕\�����A�P�R���Q�O���Ɂu�P�O�S�X���^�R�W�O�O���v�̕\�����A�P�R���Q�T���Ɂu�W�S�X���^�S�O�O�O���v�̕\�����A���ꂼ��ʉ߂����B�����āA�P�R���R�U���Ɂu�O���^�S�W�S�X���v�̕\���̂���ԓ��̏I�_�ɓ��������B���˔��A���e�i�����ї����Ă���B����Ɉ�ԍ����ꏊ��ڎw���ēo���Ă����ƁA�P�R���R�W���ɎO�p�_�������B��͂�A�P���ԂR�O���قǂ�v���Ă���B

�O�p�_�̕W����R���̕\���Ȃǂ͂Ȃɂ��Ȃ��B�������A�A���e�i���̉��̈�ԍ����ꏊ�ɂ���̂ŁA�����Ɍ�����B�x┌�M�O�R�A���s���x�A�b��x�Ȃǂ̓W�]�͔��Q�ł���B
�R���ł́A�W�]���y���݂Ȃ���A�s���H��H�ׂĂ����̋x�e�ł���B�����āA�܂����Ԃ�����̂ŁA���R�����牷��֓��邱�Ƃ͂������ł��邪�A���̑O�ɖڂ̑O�̒M�O�R�ւ��o�邱�Ƃ����߂��B�M�O�R�ɂ́A�j���͂��łɓo���Ă���̂ŁA�����o��Ԃ͒��ԏ�ő҂��Ă���Ƃ����B
����Ȃ킯�ŁA�P�R���S�U���ɂ͉��R���邱�Ƃɂ����B�R������ԓ��̏I�_�֍s�����A�������g���ߓ������āA�P�R���S�W���Ɏԓ��։��藧�����B�����ŁA���O�D�T���b�g����������B�����āA���̌�͎ԓ������ǂ����B�P�R���T�U���Ɂu�W�S�X���^�S�O�O�O���v�̕\�����A�P�R���T�V���Ɂu�P�O�S�X���^�R�W�O�O���v�̕\����ʉ߂����B�ԓ��̘H�T�Ƀt�L���Q�����Ă����̂ň�͂ݍ̎悵���B����ȓ������������A�P�S���S�R���ɃQ�[�g�܂ʼn����Ă����B�����āA�P�S���S�S���ɒ��Ԓn�_�ɖ߂����̂ł������B����͂P���Ԃقǂł���B
���āA����ŁA�o�R�C�̂܂Ԃɏ�荞�݁A���̒M�O�R���������B
�@�@�@�M�@�O�@�R�i�P�C�O�S�P���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q�T�N�V���Q�O���i�y�j����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�C���Ϗ��q�s
�@����̖k�C�������̍Ō�̎R�ƂȂ�A�M�O�R�ł���B�Ȃ�ł��Q�O�O���R�ɂ͓����Ă���炵���B���\�l�C�̎R�ł���悤���B�x┌Ή���́A���������S�T�R���Ŏx┌��E��Ɍ���`�Ŏ��v���ɉ���Ă���B��������ƁA���i���鍑���Q�V�U�����āA�E�܂��A�����S�T�R���ƍ����Q�V�R���̏d���H���ɓ���B���炭����ƁA�M�O�R�̓��H�W��������̂ŁA�����P�S�P�����ւƍ��܂���B���̓��H�͒M�O�щ����Ƃ����炵�����A�Z���^�[���C���̂Ȃ����т̒��̓��H���B���̓��H�����ւX�O�x�Ȃ���n�_�ŁA�Ȃ��炸���̂܂ܒ��i����ѓ��̓���������B���̗ѓ����M�O�R�̂V���ڂ܂Œʂ��Ă��铹�H�����A���ܑ��̓��ł���B�����ɂ́u�V���ڂ̒��ԏꂪ���t�ɂȂ����i�K�œ����������B�v�Ƃ�����������������B����قǐl�C�̎R�ł��邱�Ƃ�������B�������A�����͎������x���̂ʼn��R���Ă���Ԃ���Œ��ԏ�̐S�z�͂Ȃ��������B
�@�V���ڂ̒��ԏꂪ�߂��Ȃ�ƁA�H���ɒ��Ԃ��Ă���Ԃ��o�Ă����B�܂�ނ炪�o�R���̂V���ڂɒ������Ƃ��͒��ԏꂪ���t�ł������Ƃ������Ƃ��B�P�T���O�O���ɂV���ڂ̒��ԏ�ɒ��������A�Ă̒�A���ԏ�͔����ȏ�Ă����Ԃł������B���ԏ�͂T�O�`�U�O��قǒ��Ԃł������ŁA�g�C����V���ڃq���b�e������B
�@


�U�b�N�͂ł��邾���y�����āA���́A�T�O�O�~�����b�g���̃y�b�g�{�g�����Q�{�����āA�P�T���P�O���ɓo�R�����o�������B�P�T���P�U���ɂ͒M�O�R�Ƃ����傫�ȊŔ̂���L��ɏo���B�Ζʂł͂��邪�A�x���`�������ݒu����Ă���A�ό��q�͂����܂ŏオ���Ă��ēW�]���y����ł���悤���B


�@��������́A�{�i�I�ȓo�R���̗l����悵�Ă���B�������班���o��ƁA���т͂Ȃ��Ȃ���A�̂Ȃ��K����̓o�R���ƂȂ�B�������̎����ł͉����Ă���l����ł���B���т͂Ȃ����߁A�����m��Ϗ��q�A��ʊx�ȂǓW�]�͂��炵���̂ł��邪�A���˓����������菋���̂ɂ͎Q�����B

�@�P�T���S�U���ɓ��R�Ɛ��R�̕���_�ɏo���B�n��h�[�����͂���œ��R�Ɛ��R������A�ʏ�͓��R��M�O�R�R���Ƃ��Ă���炵���B�ڂ̑O�ɑ�`�̗n��h�[��������B���̊O���������Ɖ��悤�ɓ������Ă���B�܂��A���R�֓o�邱�Ƃɂ����B


�P�T���T�R���ɒM�O�R�R���i���R�j�i�P�C�O�Q�Q���j�ɒ������B�O�p�_������B�o�R���ł͂j�����҂��Ă���̂ŁA������肵�Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@�P�T���T�W���ɉ��R���āA���R���������Ƃɂ����B�P�U���O�O���ɕ���܂ʼn���A�O���Ɍ����鐼�R�������ĕ����o�����B�n��h�[���͉E��Ɍ���`�ɂȂ�B

�P�U���O�X���ɂ͓r���ɂ���u�M�O�R�_�Љ��{�v�ɒ������B���R�Ɛ��R�̒��ԓ_���B


��������͂�������A���̌�͐��R�����Ă̓o��ƂȂ�B�P�U���Q�U���ɗn��h�[������铹�Ɛ��R�֍s�����̕���ɏo���B���R���牄�т������ł���B


�����āA�P�U���Q�W���ɐ��R�R���i�O�O�S���j�ɓ��������B�����ɂ��O�p�_������B�܂��A���˔�����B��������Ղ���̂͂Ȃ��R�U�O�x�̓W�]�ł���B
�@�P�U���R�S���ɂ͉��R�ɂ��������B�P�U���R�T���ɕ����ʉ߂��A���H�����̂܂܈����Ԃ����B�P�U���S�X���ɒM�O�R�_�Љ��{��ʉ߂��A���R�ւ̕���ɂ͂P�V���O�Q���ɒ������B��������]����悤�ɉ����āA�M�O�R�̊Ŕɂ͂P�T���P�U���ɒ������B�����āA�P�V���P�W���ɓo�R���̒��ԏ�։��藧�����B�����łQ���ԂW�����������Ă��܂����B�����̔�ꂪ�ݐς��Ă���̂ł��낤���B
�@�����ɎԂ��X�^�[�g�����A����ɓ��邽�߂Ɂu�x�ɑ��x┌v�֍s�������A���A������́A�P�U���O�O���܂łł���ƒf���Ă��܂����B���������Ȃ��̂œϏ��q�Ɍ������ĎԂ𑖂点�A�r���ɉ�����Γ������悤�Ƃ������A����͂Ȃ��܂ܓϏ��q�ɂ��Ă��܂����B���Ȃ����Ă������A���m��ʓy�n�ŃE���E�����Ă��_�����Ǝv���A�t�F���[�^�[�~�i�����́A��ł��邪�A�P�W���̑����ɓ����������̉w�u�ނ���l�G�̊فv�֍s�����Ƃɂ����B
�@�P�W���S�T���Ɂu�ނ���l�G�̊فv�ɒ������B�����͂Q�Q���O�O���܂ŁA�H�����͂Q�O���O�O���ɃI�[�_�[�X�g�b�v���Ƃ����B�������A���q���r���ƂQ�O���O�O���O�ł��X���邱�Ƃ�����ƕ����āA��ɐH�������邱�Ƃɂ����B���j���[�́u�z�b�L�L���v�ɂ����B����̓z�b�L�L���L���炵�����炾�B���āA�H���̌�A�������Ɠ��������B���̌�A�y�Y�F���A���̓��̉w�̃I���W�i�����i���Ƃ����u��������̍��z���v���w�������B�u�������l�v���悩�낤�Ǝv�����̂ł���B
�@���āA����ȋ�łQ�O����������̂ŁA�V���{�C�t�F���[�̃^�[�~�i���ł���Ϗ��q���`�i�����j�ւƏo�������̂ł������B���H�͑����m�t�F���[�ŕ��H�͐V���{�C�t�F���[�Ȃ̂ł���B
�@�o�`�͂Q�R���R�O���ł��̂Q���ԑO����葱�����J�n����Ƃ����̂ŁA�Q�P���R�O���܂łɒ����悩�����̂ł��邪�A�\���ɊԂɍ������B�葱�����ς܂��Ĕ��X�Ńr�[�������ݏo�`��҂����B�Ԃ��^�]���ăt�F���[�ɏ�D���邽�߁A�܂��A�r�[���͈��߂Ȃ������B��q�͂Q�Q���S�T�������D�J�n�ŁA�ԗ��͂Q�R���O�O�������D���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�@�ԗ��̐ςݍ��݂��x�ꂽ���A����ł��\��ǂ���Q�R���R�O���ɏo�`�����B�����A�r�[���ʼn�����n�߂��B�����Q�P���i���j�̂Q�O���R�O���ɓ։�`�֓��`�\��Ȃ̂ŁA�r�[���͒��܂ł������߂Ȃ��B����Ȃ킯�Ńr�[��������ŏA�Q���A�����������邱�Ƃɂ����B�D���͌����ł悭���ꂽ�B�����͂W���O�O������ł������̂ŁA�������C�֓���ɍs�����B�I�V���C��������K�ł���B�����͓V�C���悢�̂łȂ�����ł���B���C�オ��ɂ͑����r�[���ł���B���H�̂��߃��X�g�����֍s���A�r�[�������B�̂���A�����C�A�����͍��Y��ׂ��Ƃ����Ă��邪�A���ꂾ���C�������悢�Ƃ������Ƃ��B
�@���āA���H�̂��Ƃ́A�܂��D���A���ăr�[���ł���B���̌�A�Q�Ă��܂��Č��ǒ��H�͔����H�ڂɂȂ����B�[�H�́A�܂��܂����X�g�����Őۂ邱�ƂɂȂ������A�����������r�[���͈��߂Ȃ������B�[�H��́A�f�b�L�ɏo�ė[���������B���̋�ɂ͉_�������������Ƃ��T���Z�b�g�͌��邱�Ƃ��ł����B���̌�́A�܂����C�֓����Ă���A�D���֓����ĉ��ɂȂ��ċx�������B�։�ɂ͒荏�̂Q�O���R�O���ɓ��`�����B���D�́A����҂��Ԃɏ���Ĉꏏ�ɉ��D���邱�Ƃ��ł����̂ő��������B
�@���D��A�����W���Ŗk�������ԓ��̓։�h�b�܂ŗ��āA�����ɏ��ւh�b�ō��������肽�B�����āA�֎s�ւQ�Q���O�T���ɒ����A�����Ŏ����̎Ԃɏ�芷�����B�Q�Q���P�V���ɏo�����A�Q�Q���S�T���ɋA����̂ł������B�����k�C�������̊����ł���B�����͎d�������A�����Ɨ��s�p�i��Еt���Ă���A�Q�����B